連載
#10 平成炎上史
「無敵の人」を生み出したのは誰?「黒子のバスケ脅迫事件」の問い

平成の時代に始まったネット炎上は、当初から、背景にある要因の一つとして「社会的孤立」の問題を抱えていた。その結果、生まれたのが「無敵の人」である。「ネット上のトラブルに執着する」ような人を生み出したのは誰か? 「秋葉原無差別殺傷事件」「黒子のバスケ脅迫事件」から見えてきたのは、世の中に認められない「孤独」の根深さであり、誰もが「無敵の人」になり得る危うさでもあった。(評論家、著述家・真鍋厚)
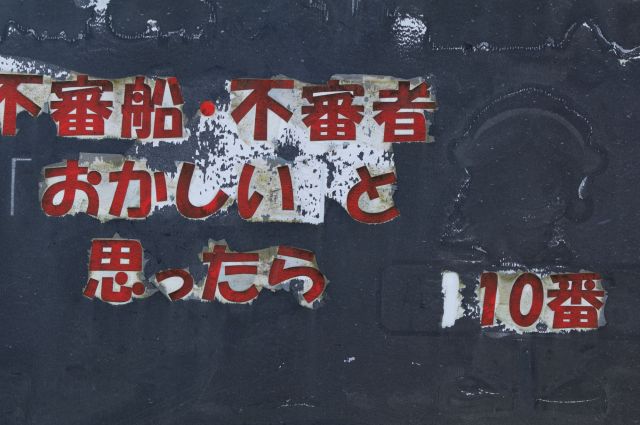
西村氏の指摘は、時期的に2008年6月8日に起こった秋葉原無差別殺傷事件を意識したものと思われる。
犯人の加藤智大死刑囚は、当時の自分が置かれていた状況について、自身の心境をつづった手記『解』(批評社)でこう述べている。
「私の社会との接点は、掲示板でのトラブルだけ」
「そこから離れると孤立することになるため、孤立の恐怖は耐えがたく、私はトラブル相手にしがみつきました。そこから事件へと向かっていく」
手記の中で「荒らしとのトラブル」が直接の原因であったことを自省の念とともに振り返っているのが示唆的だ。
ここでもう少し丁寧に見なければならないのは、「荒らしとのトラブル」とある通り、「荒らし」(嫌がらせの書き込みを行うネットユーザー)も、実は「無敵の人」とかなり近いところにいる存在であることだ。
前述のトラブルとは、自分が立てた電子掲示板に、「荒らし」や「なりすまし」といった迷惑行為をする者が現れ、それらとの間で、いさかいが勃発したことを指し示している。
そのことで自分の居場所が奪われたと感じ、それがいかに不愉快なことであるかを認識してもらうため、秋葉原無差別殺傷事件を起こしたというのが主な動機であることを見てとれる。まさに「関係性」が「掲示板のみ」となった特異な状況が、「荒らし」の集団を「自分にとっての最大の敵」に変えたのである。
つまり、「社会との接点が掲示板でのトラブルだけ」という人物と、それを面白がって「荒らし」「なりすまし」になって炎上させる人物たちが「最悪の形で出会った」という視点が重要なポイントになってくる。
加藤死刑囚に象徴される「無敵の人」はあまりにも極端な例(社会的孤立が凶悪犯罪に直結すること自体がまれ)だが、(法的リスクのあるものを含む)「恥知らずな言動」を繰り返して心がいたまないネットユーザーに、すでに「無敵の人」になりかねないキャラクターの萌芽(ほうが)が色濃くにじみ出ている。

掲示板で加藤死刑囚をもてあそんでいた側にも、「関係性の貧困」があったことが想像に難しくない。これをとりあえず「準無敵の人」または「無敵の人予備軍」と呼びたい。
「準無敵の人」「無敵の人予備軍」も、「無敵の人」と同じく「関係性の貧困」と、アイデンティティーの危機にさらされている。
仕事や家庭があって普通に暮らしているように見えても、「ある種の不全感、不幸感」に悩まされていることが多く、ネットというコミュニケーション空間に依存しやすい状況にある。そこで自分が何者であるかを明確にするため、他者の差別につながる「自他を峻別する」価値観や、過激な政治的主張に傾いてしまう場合がある。
その際、リテラシーの低さや法的リスクへの疎さから、ネット上で簡単に誹謗(ひぼう)中傷や脅迫まがいの言動を行ったり、それらに加担してしまう。
社会学者のジョック・ヤングは、「アイデンティティと社会的価値を保持している感覚が他者に尊重されること」を「承認の正義」と呼び、それが危険にさらされることを「承認の不全あるいは存在論的不安」と表現した(『後期近代の眩暈 排除から過剰包摂へ』木下ちがや訳、青土社)。これが様々な逸脱行動の源泉となる。
令和の時代に入っても絶えないニュースサイトのコメント欄やソーシャルメディア上で野放図に燃え広がる「不謹慎狩り」や有名人へのバッシング。これらは、「不謹慎」という「大義」の名の下に他者を血祭りに上げることにより、自己を「大義の側に組み込む」だけでなく、バッシングをする行為に心地よさを感じる「自意識に軽い酩酊(めいてい)」をもたらしてくれる。
つまり、悪や不正の告発や、不快の表明を口実に「懲罰する側」に回って、「正義感」や「達成感」などを満たすことで自己肯定感を得るのだ――そこからは「自意識と能力をもてあました」「社会的なつながりや評価に飢えた」人々の姿が浮かびあがる。
たとえ、経済的に多少の余裕があっても、「他者からの社会的な承認」が不足していると自分に自信を与えてくれる「自尊感情」が脅かされるからだ。だが、根本的な問題が解消されることはないため、「不謹慎狩り」のような行為を繰り返さざるを得なくなる。無自覚な「ソーシャルメディアの兵器化」である。このような「ソーシャルメディアの兵器化」の心理について「社会的孤立」の観点から明らかにした当事者の声がある。
「無敵の人」という言葉が再び話題になった2012~13年(平成24~25年)の「黒子のバスケ」脅迫事件の渡辺博史被告(当時)が語った初公判での意見陳述だ(以下、月刊『創』の篠田博之編集長がまとめた「被告人の最終意見陳述全文公開(https://news.yahoo.co.jp/byline/shinodahiroyuki/20140315-00033576/)」から引用する)。
彼は自らの犯罪を「人生格差犯罪」と名付けた。「自分が『手に入れたくて手に入れられなかったもの』を全て持っている」人物「を知り、人生があまりに違い過ぎるとがくぜんとし、この巨大な相手にせめてもの一太刀を浴びせてやりたいと思ってしまった」と主張したのである。
これはネットバッシングの「隠された欲望」にありがちな〝誠実な回答〟として読むことができる。その背後には「努力を強いられる」社会における「報われなさ」があり、「自制と犠牲の経験こそが、素朴な不満(不公平だという感覚)を復讐(ふくしゅう)心に転化させる」(『後期近代の眩暈』)のだ。

「復讐心」は自己肯定感を得るために必要なアイデンティティーの輪郭を「一時的に作り出す」が、すぐに不安定な自分と向き合わざるを得なくなる。これは情報の民主化、ネットによる相互監視による嫉妬が蔓延(まんえん)した現代では、決してひとごとで済ますことはできない
渡辺被告(当時)は、とても分かりやすい表現で、非常に重要な問題提起をしている。
彼は「社会的存在」と「生ける屍」という二つのカテゴリーを示し、後者は、「感情や規範を両親から与えられず、人や社会とつながっていない」存在と述べた。
上記の文章は、わたしたちに自己肯定感を得られない絶望的な境遇を的確にイメージさせる。その上で彼は、「人間がなぜ自分の存在を認識できるのかというと、他者が存在するから」と言い、「自分の存在を疑わないのは他者とのつながりの中で自分が規定されているから」と説明している。

「生ける屍(しかばね)」という言葉で思い出すのは、先月来日したローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇の発言だ。日本における「社会的孤立」の問題に触れていたのである。
教皇は、このような核心を突いた指摘を行い、「霊的な貧困との闘いは、わたしたち全員に呼びかけられている挑戦」であることを強調した。「霊的な貧困」とは「関係性の貧困」とほぼ同義であると読み取れる。今の日本において「社会的存在」と「生ける屍」の間に境界線などないような状況になってきている。
誰もが孤立のリスクからは逃れられない。わたしたちはこの「挑戦」にどのように立ち向かうかが試されている。

1/4枚