ARTICLE
本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業
(厚生労働省補助事業)として実施しています
(実施主体:朝日新聞社)

広告特集 企画・制作
朝日新聞社メディア事業本部
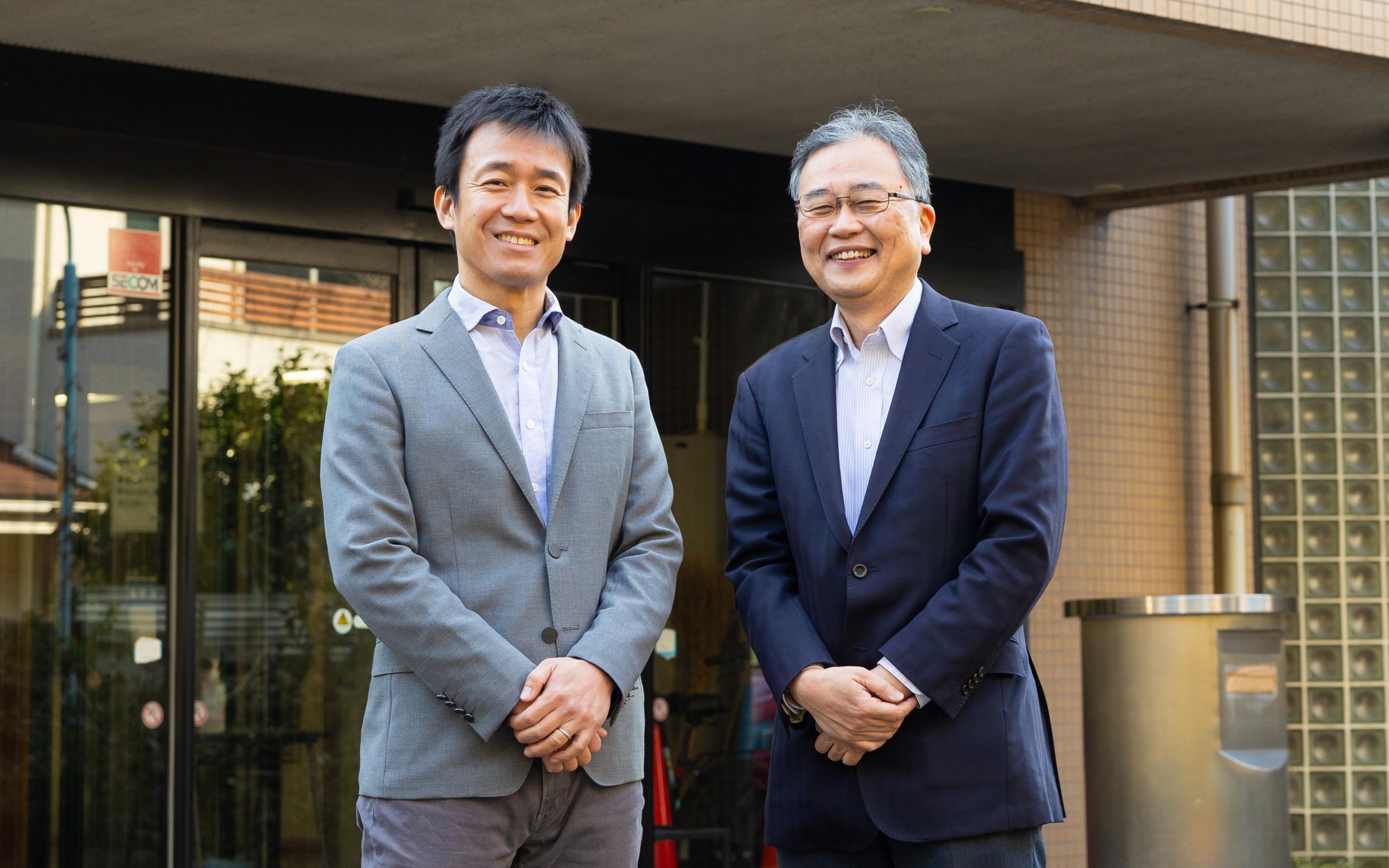
一言で「視覚障害」といっても、障害の程度にはいろいろなレベルがあります。まったく見えない人もいれば、光を感じることができる人、視界はぼんやりしていても、何かが動いていることはわかる人などさまざま。東京視覚障害者生活支援センターでは、このような視覚障害のある人々が訓練しています。同センター所長で社会福祉士の石川充英さんと機能訓練に携わっている小林一哉さんに、訓練の実際や思いを伺いました。
石川充英(いしかわ・みつひで)さん
1986年に東京都視覚障害者生活支援センター(現・東京視覚障害者生活支援センター)に入職。就労支援課長を経て2023年4月より所長。長年にわたり視覚障害者支援に関わってきた。視覚障害者の「歩行訓練」「パソコン訓練」といった二つの領域における支援に尽力し、論文・講演など多数。
小林一哉(こばやし・かずや)さん
機能訓練の支援員。大学生のときに全盲の小学生の家庭教師をしたことがきっかけで、学校教育・特殊教育に興味を持ち、盲学校の教員免許を取得。大学卒業後は福島県内の知的障害養護学校で1年間働いた後、2002年4月、東京視覚障害者生活支援センターに入職。以降、機能訓練などの支援員として働いている。

東京視覚障害者生活支援センターは、「見えない人・見えにくい人」たちの「機能訓練」と「就労移行支援」を行なう多機能型事業所です。運営しているのは、社会福祉法人・日本盲人社会福祉施設協議会。かつては東京都の委託を受けていましたが、2017年に東京都の指定管理から同法人に民間移譲されました。
東京都新宿区内で地下鉄駅の近くという立地もあって、都内だけでなく、千葉県・埼玉県・神奈川県から通う利用者もいます。
所長の石川さんによると、利用者の障害レベルは幅広く、まったく見えない人が2割、残り8割はロービジョンの人だそうです。生まれつきではなく、病気やけがが原因で視覚障害になった方が多いといいます。
機能訓練では、白杖(はくじょう)歩行や点字、スマートフォンにパソコン、調理や裁縫といった幅広い技術の習得を目指します。また臨床心理士がケースワーカーを担当しており、トレーニングと同時に利用者の心理的なケアも行っています。
一方の就労移行支援では、就職や復職を希望する人を対象に、パソコンのスキルやビジネスマナーなどを身につけることを目指します。就職面接試験への同行など手厚いサポートの効果もあって、定員15名の半数以上の方が就職、または復職しています。
同センターでは利用者の現状と希望を照らし合わせて、目標や訓練内容を決めます。生活スタイルや住居環境、家族構成などによって、習得したい技術やレベルが異なるため、とのこと。石川さんは「個別に支援計画書というものを作り、訓練内容と目標を決めます。習熟スピードが早い場合は、計画書の変更を相談することもあります」ときめ細かい支援を説明します。
視覚障害者の機能訓練と聞くと、白杖による単独歩行訓練や点字訓練を思い浮かべる人もいるでしょうか。しかし最近はICT(情報通信・伝達技術)が進歩して、スマートフォンやパソコンにもアクセシビリティ(身体の状態や能力の違いにかかわらず、さまざまな人が利用しやすい状態)機能が備わるようになりました。それによって視覚障害者の機能訓練の内容も大きく変化しました。「コミュニケーションのトレーニングでは、スマートフォンやパソコンが人気です」と支援員の小林さん。
パソコンの訓練では、画面の情報を読み上げるソフト(スクリーンリーダー)を使うなどして、文書作成やメールでのやりとり、ウェブサイトなどの操作を練習します。機能訓練では、文書作成や表計算のソフトに加えて読書や音楽、ネットショッピングといった生活に根ざした使い方もトレーニングしています。
「スマートフォンの訓練では、搭載されているスクリーンリーダーの機能を使い、情報収集・情報発信やコミュニケーションをとるトレーニングも積んでいます」と小林さん。

さらに近年では、OCR(画像やスキャンした文書から文字を自動で認識、抽出する技術)にAI(人工知能)を採り入れた便利なアプリが次々にリリースされるようになりました。小林さんは「数ある中から利用者のニーズに合ったアプリを紹介して、上手く活用できるようにトレーニングをしています」と説明します。
さらに「例えば歩行支援アプリは、GPSによる誤差などリスクを含むものの、点字ブロックや信号機の変化、自転車が横を通過する際に音声で知らせてくれます。他にも色を識別するアプリ、紙幣を識別するアプリなどたくさんあります」と現状を紹介してくれました。
デバイス(端末)やアプリ、ソフトウェアは日々、新しい機能などが生まれています。小林さんは「利用者に情報を提供できるよう、常にアンテナを張って新しい情報をキャッチしている」と情報収集に余念がありません。逆に、利用者から便利なアプリを教えてもらうこともあるそうです。
電子デバイスは一般的に、高齢者ほど扱い慣れない傾向があると言われています。小林さんがサポートしている利用者にも同様の傾向は見られるそうですが、日々の訓練で克服しているといいます。小林さんは「状況や場面によってスマートフォン・パソコンを使い分けている」と話します。

スマートフォン・パソコンで便利になる一方、新たな注意点も生まれました。そのひとつはデバイスの操作性です。「スマートフォンはフラットな画面をタップするので、きちんと押せているかどうかが分かりにくい。操作方法が繊細な点もネックです」と小林さんは指摘します。
例えば画面を1本指で右に払うとカーソルが右に移動して部分的に読み上げる。2本指で下にスワイプすると全画面を読み上げる。3本や4本での操作もあります。タップも1回と2回で指示内容が異なります。さらには「ホールド」という動きも……。「正確に操作するには、それなりの習熟が必要です」と小林さん。
課題はOCRの機能にもある、と小林さんはさらに指摘します。「AI機能が向上してかなり聞き取りやすくはなりましたが、例えば数字を知りたいなど正確性が不可欠なシチュエーションにおいて、ある程度の間違いはやはり発生してしまう状況です」。小林さんは「OCRやAIはさまざまなアプリが登場しているものの、まだまだ100%正確な情報を提供しているとは言いにくいようです」と話します。
そして小林さんは強調します。「どれかひとつのアプリだけでは、足りない情報を完璧に補うことはできません。状況や場所によって電子デバイスや点字やICレコーダー、サポーターの手などをうまく組み合わせることが重要なのだと思うようになりました」
こうしたスマートフォンの台頭は、一方で、「利用者の選択肢を狭めている」と石川さんは指摘します。
それ以前に広く使われていたフィーチャーフォン(ガラケー)が急速に減少。その結果「スマートフォン“一択”ともいえる状況になって、利用者がどちらか好きなほうのデバイスを選べなくなってきている」と石川さん。
石川さんはさらに「スマートフォンによって利便性を得られた半面、視覚障害者はボタンのあるガラケーの利便性を失うことになった。それによって生じた不利益も無視できません」と強調します。
支援員の小林さんは、点字にも課題があると指摘します。
点字はハードルが高く、途中で習得をあきらめる、あるいは最初から習得を希望しない利用者もいるそうです。大人になってから視覚障害者になった人や高齢者の中には、指の皮が硬くなって点字を読み取る感覚が鋭敏ではなくなってしまっているケースも見られるとのこと。
「でも点字の重要性は、変わりません」と小林さん。「例えば災害時など充電が難しい環境では、スマートフォンは電源がなくなったら役に立たなくなります。いざという時の選択肢がゼロでは困りますし、選ぶことのできない状態では自立しているとは言えません。そういった観点からも点字などのアナログ媒体も大切なのだと考えています」
ICTの進化で利便性が増すがゆえに、敬遠されてしまう点字。視覚障害者支援の悩ましい課題といえそうです。
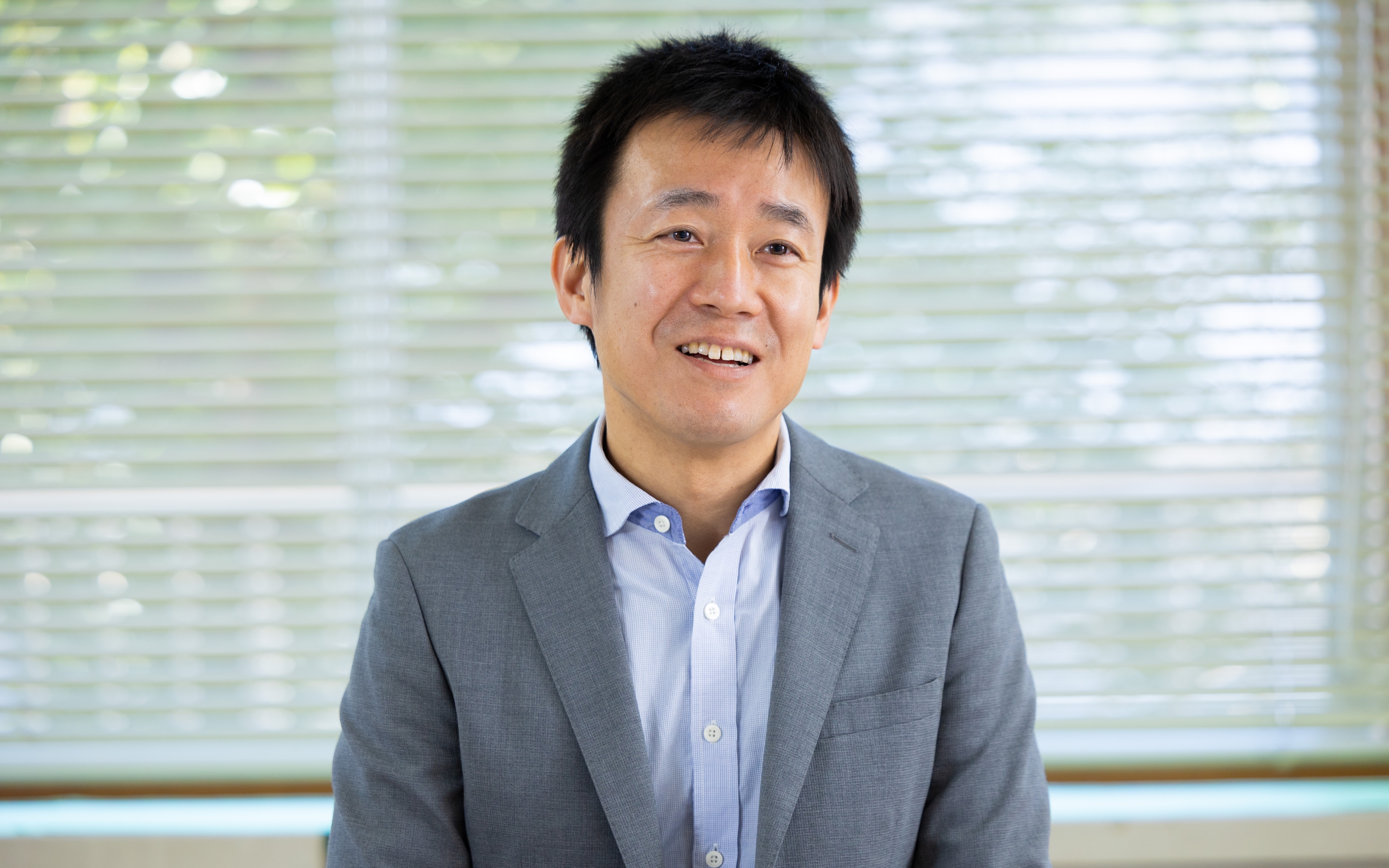
機能訓練や就労移行支援を総称して、視覚障害リハビリテーションと呼ぶことがあるそうです。石川さんは「例えば骨折などのけがや脳梗塞などの疾患での『リハビリ』は一般的です。一方、視覚障害のリハビリテーションはあまり知られていないと感じます。このような『リハビリ』の存在を広めることも施設の役割と感じています」と説明します。
その「視覚障害リハビリテーション」について、石川さんは「それは視力の回復を目的としたものではなく、見えにくい・見えないことを用具の活用や技術の習得で補うための訓練となります」と解説します。「視覚障害になった方には、視覚障害リハビリテーションを受けていただき、生活の質の向上につなげていただきたいと思っています」
視覚障害者のリハビリテーションの施設として活動を展開する東京視覚障害者生活支援センター。その機能訓練の最前線で働く小林さんは、日々変化していく利用者と直接関われることにやりがいを感じているといいます。
「利用者のみなさんはここで、どんどん変わっていきます。例えば音響信号がついていない横断歩道で、アプリを使って青信号を確認して単独で横断できるようになったとか、冷蔵庫のどこに何が入っているのかが分かるようになったとか……。トレーニングをすれば、すぐに結果が表れて喜んでいただけます」
急に視覚障害者になったことで、落ち込んだ状態で施設を訪ねてくる人もいるそうです。「しかしここでトレーニングを積んで、出来ることが広がることで前向きになり、自分の力でどんどんと吸収していく姿を見ていると、素直にうれしいです」と小林さん。
東京視覚障害者生活支援センターでは、「視覚障害のある方が一人でも多く、自らの力で問題解決できるようになってほしい」と願いながら、職員のみなさんが今日も、利用者のトレーニングに伴走します。
本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業
(厚生労働省補助事業)として実施しています
(実施主体:朝日新聞社)