コラム
「自分は必要のない子」生きづらさの背景に〝家族問題と自己肯定感〟
幼少期の虐待が、いまもトラウマに…

家族関係は、これほどまでに自己肯定感に影響を与えるのかーー。毒親や家庭内暴力(DV)の取材で当事者に話を聞くと、多くの人が自己肯定感の低さを語りました。特に子ども時代の苦しみは、大人になっても人生に暗い影を残します。取材を通して、生きづらさを和らげるヒントを考えました。(朝日新聞編集委員・岡崎明子)
「わたし、自己肯定感が低いんです」
昨年4月から、「毒親」「妻から夫へのDV」「不機嫌ハラスメント」など、家族関係の悩みを抱える当事者に話を聞く取材が増えました。ほとんどの人が話の途中で、自己肯定感の低さを吐露します。
なぜ家族関係の問題と自分を肯定する感覚はつながっているのか。そんな疑問が連載「わたしの敵はわたし? 自己肯定感と向き合う」の出発点でした。
昨年夏。都内のある喫茶店で、毒親からの仕打ちが今もトラウマになっているという女性に話を聞いたときのことです。
その女性は取材の間じゅうずっと、おしぼりを握りしめていました。あまりにも強く握っているため手は真っ赤になり、震えていました。
保育園のお迎えを忘れられて夜9時過ぎまで1人で待っていたこと、弟の面倒を見ないと下着姿で外に出されたことなど、幼い頃から虐待を受けてきたそうです。
次第に「自分は必要のない子なのだ」と思うようになったといいます。
結婚生活も、子どもとの関係もうまく築けず、カウンセリングに通い続けている女性は、こう漏らしました。
「生まれてこなければ、こんな思いをしなかったのに」
今も自分を肯定することができないと、蚊の鳴くような声で話しました。
おしぼりを握りしめることで、なんとか気力を振り絞っていたのでしょう。「親からの愛情は、これほどまでにその人の自己肯定感に影響を与えるのか」と、改めてショックを受けました。
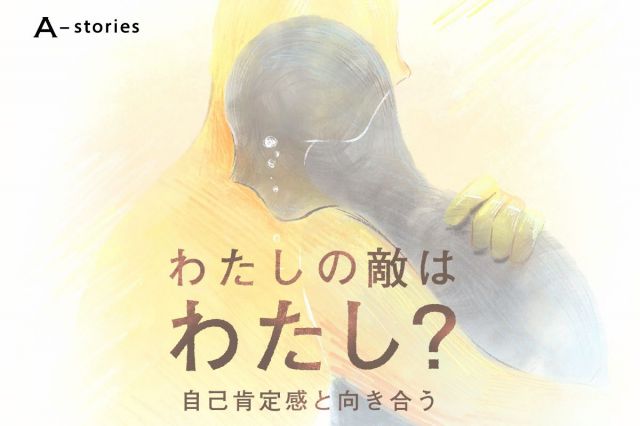
さらに、大人になった今も家族関係に悩む人たちにとって、自己肯定感の低さが人生に深く影響していることにがくぜんとしました。
連載の初回で取り上げた女性も、小学生のときに突然母が失踪し、「自分は捨てられた」という思いをずっと抱えて生きてきました。
全国模試で1位を取って京大に進んでも、就職しても、人間関係につまずき「自分は愛される資格がない」と話していました。
自己肯定感を持てない感覚を、女性はこんな言葉で表現しました。
「自分を構築する『基盤』にヒビが入っている」
連載に登場したほかの女性も、同じような表現をしていました。
「自分を構築しているのは、『不安』」
そうか。親や周囲の大人との関係は自身を構築する基盤なのに、そこが不安定だと、自分という土台がないことと等しいのか。
だから、いろんな人やモノに依存したり、自分を傷つけたりする人をパートナーに選んだり。いくら努力しても「自分はまだまだ駄目だ」と認められず、頑張り続けてしまう。そして、メンタルを崩してしまう。
今まで取材してきた方の生きづらさが、「自己肯定感」をキーワードにつながりました。

我が身をふりかえってみると、どちらかと言えば、自己肯定感は低い方だと思います。
昭和生まれの私の両親は、「いい気にならないように」と、私をあまりほめて育てませんでした。そのせいか、いまだに何かをほめられても、素直に受け取ることができません。
専門家によると、自己肯定感の低さとうまく折り合うためには、「小さな成功体験」を積み重ね、自分をほめることを日課にするとよいそうです。
私も年齢を重ね、だいぶ図太くなってきたせいか、昔よりは自分を肯定できるようになったと感じます。
自己肯定感は低いより高い方がよいとは思います。ただ、そのことに必要以上にとらわれることも、かえって自分を苦しめてしまうのではないか。取材を通じて、そう感じました。
自己肯定感が低い自分も含めて、「まあ仕方ないか」と受け入れること。それが生きづらさを和らげるコツなのかもしれません。

1/131枚