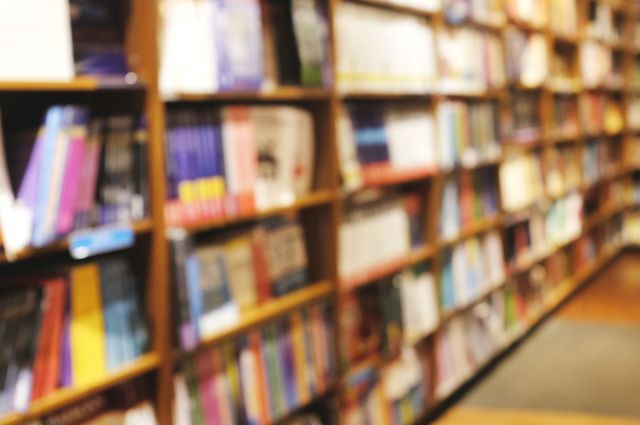ヤンデル先生:先ほどのトークで、小児科医の堀向健太先生がマスクをしなかった患者さんに対して、診察室での的確な対応で、少しずつコミュニケーションをとることでマスクをしてくれるようになった、というお話があったじゃないですか。
【トーク採録記事はこちら】外来に「マスクをしたくない」患者が来たら…医療不信との向き合い方
これは、「世の多くの人に届かないから私達は無力である」っていう話とは、全然違うんですよね。堀向先生は、診察室の中という極めて狭い場所ではあるけれど、着実に患者さんにリーチしている。それはすばらしいことだと思います。
ところで、ひとつのデマに踊らされてる人って、たぶん人口の1%とかじゃないでしょうか。でも、そのデマが無数にあるから、人口の何割ぐらいかが踊らされることになってしまっている。ひとつひとつのデマが刺さる人たちの割合って、僕はそんなに大きくないんじゃないかなと思っています。
ターゲットを狭くした情報というものをわれわれももっと出すべきなんだけど、今もひと世代前のやり方を続けていて、「マス」に届けてみたいと思ってしまっているんです。
ならばわれわれは、たとえばAIを使って、「このクラスターに対してはこの情報が必要だ」という見極めをするなど、工夫をしなければいけないと思うんですよね。
大須賀先生:アメリカでも、AIを使うとか、サイエンスコミュニケーションでどうやったらリーチできるのかをものすごく研究している人たちがいます。
ヤンデル先生:それは研究機関とかと組まないと、個人で発信している医療従事者自身はなかなかできないと思います。ただ、それで終わるといけないので、自分がちゃんと顔を見たことのある人たちをイメージして、そこに届くようなコミュニケーションをしっかりやる……という原則に立ち返るしかないんですよね。
「もっと多くの人に見てもらえれば解決だ」というのは幻想で、ターゲットを絞っていかなければいけないということですね。