連載
#26 Busy Brain
大学時代70キロ近くの体重に。30歳まで続いた小島慶子さんの過食嘔吐
吐くと、少し自分が清くなるような気がしました

40歳を過ぎてから軽度のADHD(注意欠如・多動症)と診断された小島慶子さん。自らを「不快なものに対する耐性が極めて低い」「物音に敏感で人一倍気が散りやすい」「なんて我の強い脳みそ!」ととらえる小島さんが綴る、半生の脳内実況です!
今回は、大学時代に過食嘔吐を繰り返してやめられずに10年以上摂食障害に苦しんだ経験を綴ります。
(これは個人的な経験を主観的に綴ったもので、全てのADHDの人がこのように物事を感じているわけではありません。人それぞれ困りごとや感じ方は異なります)
食べ方がおかしくなっていたところへ拍車をかけたのが、失恋です。
高校3年生の終わり頃から、付属の大学の3年生たちと一緒に遊ぶようになりました。同級生の兄とその仲間たちです。やがてその中の一人と交際。大学入学とほぼ同時に、4年生の彼氏ができたのですから鼻高々でした。
その人は大手企業に内定していたので「やった! このまま結婚すれば、お姉ちゃんと同じ幸せが手に入る!」と安心しました。初めての恋愛にもっと浮かれてもよかったのに、あまりにも「母や姉のように“幸せ”にならねば」というプレッシャーが強かったので結婚のことばかり気になっていたのですね。
いい人だったのですが、前の彼女にふられた傷が深く、結局は半年ほどでふられてしまいました。
恋愛中は太らないように気をつけていたものの、体育会系の4年生男子たちと一緒に行動するうちに摂取カロリーが増え、確実に体重は増加していました。失恋と同時に糸が切れ、それまではチューイングといって口に入れてはぺっと吐き出す行為で食欲をごまかしていたものが、ついに飲み込んでしまうように。
食欲がコントロールできなくなり、深夜までテレビを見ながらお菓子を貪る過食状態になりました。家中のお菓子を食べ尽くし、やがてはバイト代を食べ物に注ぎ込むようになりました。バイト帰りに自宅の最寄りのバス停で降りると、商店街のお店を梯子(はしご)してお菓子を買い込み、家に戻ったら母に見られないように自室に直行。しかしいくら食べても満腹にならず、むしろますます食欲が強くなりました。
食べているときは天国でした。頭が空っぽになるのです。食べていれば、ふられた惨めな自分のことを考えずに済みました。食べて自分を忘れ、太った姿を見て自己嫌悪がひどくなり、そんな自分を忘れるためにまた食べる。食べ物依存症です。50キロ台だった体重は瞬く間に70キロ近くまで増えました。全ての服が入らなくなり、何をするにも体が重く、散らかった部屋で雨戸を締め切って、買い込んできたお菓子をひたすら食べました。三段腹って本当に3つの段になるんだなあと他人事のように腹肉をつかんで、毛玉だらけの同じ部屋着を着続けました。
おそらく母は幼い頃からその整った容姿に注目されることが多かったのでしょう。かなり外見を気にする人でした。ひょろりとしていた娘が見たこともないような巨体になっていくのを見て、「オランウータンみたいね」と言った口調からは、嫌悪と失望が感じられました。理性を失ったように食べ続ける娘の様子に、母もどう対処していいかわからなかったのでしょう。

その頃から私は、食べては吐くようになっていました。過食嘔吐です。吐くのは、それ以上太りたくなかったから、そしてもっと食べたかったからです。古代ローマの貴族がご馳走を食べ続けるために羽根で喉をつついてわざわざ吐いたという話を聞いたことがありますが、私も同じでした。もっとも、贅沢なご馳走を楽しむためではなく、自分を呪い蔑みながら食べるためでしたが。
吐くと、お菓子と一緒に何か重たいどろっとしたものが出て行って、少し自分が清くなるような気がしました。これで明日から生まれ変われる。もう食べるのをやめられると思っては、またお財布が空になるまでお菓子を買うことの繰り返しでした。
毎日毎日、脱ぎっぱなしの服と空き容器が散らばった穴蔵みたいな部屋にぺたりと座って、泣きながら食べ続けました。顔を映さないで済むように壁から取り外して床に置いた鏡に、ちょうど服からはみ出たお腹が映っていました。わざと乱暴に口にお菓子を詰め込みながら「ざまあみろ、お前なんて死ねばいいんだ」と鏡に向かって念じていました。そうやって自分を侮辱すると、痛痒いような快感を覚えました。同時に、心底死にたかった。自分をいじめることがやめられなくなっていました。
結局、この過食嘔吐は30歳まで続きました。無理なダイエットで体重を落としてアナウンサーの試験を受け、テレビに出るようになっても過食は止まらず、会社でも人目を盗んで食べては吐いていました。
当時のテレビ局の社内には社食やカフェがいくつもあり、お菓子をたくさん売っている売店もあったので、食べ物はいくらでも調達できました。トイレも各階に何カ所かあるので、人気のない場所を選べば気づかれることがありません。
仕事をすればするほど自己嫌悪がひどくなって、自分を忘れるために食べてしまう。職場でこっそりお酒を飲んでしまう人と同じです。そうする以外に、大嫌いな自分自身と一緒に生きていく方法を思いつきませんでした。

この間に、交際した人たちもいました。結婚もしました。彼らは私の食べ吐きには何も言いませんでした。気づいていなかったのか、ダイエットしていると思っていたのか、見て見ぬ振りをしていたのか。本当は、誰かが「それは何かおかしいよ。心配だよ」と受診を勧めてくれればよかったのかもしれませんが、当時は私自身も病気だとは知らなかったし、もしも恋人や夫に指摘されたら恥ずかしさのあまり逆上していたでしょう。
病気だと知ったのは、30代後半になってから。偶然、摂食障害の記事を読みました。これは、かつての私と同じじゃないか。私だけの恥ずかしい癖じゃなくて、あれは病気だったんだ!仲間がたくさんいるんだ……と、心底ホッとしました。
それでも、過食嘔吐の経験を話せるようになるのにはさらに何年かかかりました。「みっともない」「意地きたない」と言われるのではないかと怖かったのです。やめたくてもやめられないことを理解してもらえないだろうとも思いました。
のちに仕事でパチンコ依存症の取材をしましたが、他人事とは思えませんでした。私がいちばん手に入れやすいのは食べ物だったけど、お酒が身近ならアルコールだったろうし、近所にお店があればパチンコだったかもしれない。セックスや買い物だったかもしれないし、薬物だったかもしれない。
たまたま私の場合はそれが食べ物だったというだけで、何かに依存しないと生きていられないしんどさは同じかもしれないと思いました。ただ、何に依存するかで健康被害や違法性などの程度が異なるため、その点摂食障害は、単なる食いしん坊だろうとかダイエットだろうとか、あまり深刻に受け止められないのかもしれません。

でも当時の私は食べ吐きをやめたくてもやめられず、経済的損失も大きく、生活の質が著しく損なわれていました。食べ吐きは、リストカット同様の自傷行為でもありました。吐いていると、生きている実感があったのです。吐き続けて胃が裏返るような痛みを感じた後、空っぽになった体は緊張がほぐれて軽くなり、温かな血液がさあっと流れ出すような爽快感を覚えました。
食べ尽くし吐き尽くしてから部屋をきれいに掃除して整えると、その時だけは前向きな気持ちになれました。その時だけは、明日はあるべき自分になれるだろうという気がするのです。大嫌いな惨めな自分はもうこれで終わりと心に誓って、安心して眠ることができました。それを毎晩繰り返していました。
生まれ育った原家族との関係に悩みカウンセリングを受けるようになってからも、このことは話しませんでした。カウンセラーには他のことはなんでも話せたのに、食べ吐きのことだけは恥ずかしくて話せなかったのです。もう一生やめられないと思っていた過食嘔吐をやめることができたきっかけは、初めての出産でした。
新生児の育児でてんてこまいで、過食どころではなくなったのです。気づいたら、もう食べ吐きをしたいとも思わなくなっていました。後付けの理由ですが、子どもを産んだ途端、それまでの関心の中心だった自分自身が横に追いやられ、子どもで頭がいっぱいになったからではないかと思います。
私のおしゃべりな脳は新しくて強い刺激に関心が移りやすいようですから、目の前に現れた新生児に夢中になって、自分自身や食べ物への興味を失ったのかもしれません。
過食嘔吐の症状がなくなってからもう18年ほど経ったいまは、食べたいものを好きなように食べても以前のような異常な食べ方にはならず、ちゃんと満腹になります。食べ過ぎてしまうのではないかという心配もなくなりました。好物の和菓子を何個も食べることもありますが、それは楽しんでいるので心配にはなりません。何かを忘れるために食べているわけではないからです。
時々ふと「ああ私は本当に治ったのだなあ。それにしてもよくやめられたものだ」と思います。おそらく育児で忙しくて過食嘔吐ができなくなった後に発症した不安障害の治療の過程で、摂食障害の根本にあった生きづらさも治癒していったのだと思います。本当に幸運でした。
ただ、もっと早く病気だと気づいていれば、10年以上も苦しまずに済んだのにと思います。いま、食べ方が極端になってしまってやめられずに悩んでいる人や、家族や友人の食べ方がおかしくなって気になっている人は、専門家に相談すれば治療することができると知って欲しいです。
同じことに苦しんでいる仲間も、助けてくれる人もいます。今でも、「ここから抜け出したいけど、誰にも知られたくない」というあの頃の気持ちを思い出すと、胸が苦しくなります。もしも身近な誰かの異変に気づいた時には、責めたり問い詰めたりせず、相手が安心して話せるように声をかけてあげてほしいです。
(文・小島慶子)

小島慶子(こじま・けいこ)
エッセイスト。1972年、オーストラリア・パース生まれ。東京大学大学院情報学環客員研究員。近著に『曼荼羅家族 「もしかしてVERY失格! ?」完結編』(光文社)。共著『足をどかしてくれませんか。』(亜紀書房)が発売中。
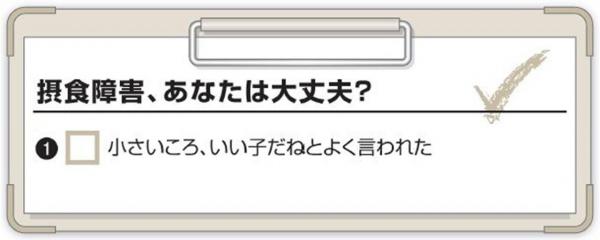
1/11枚