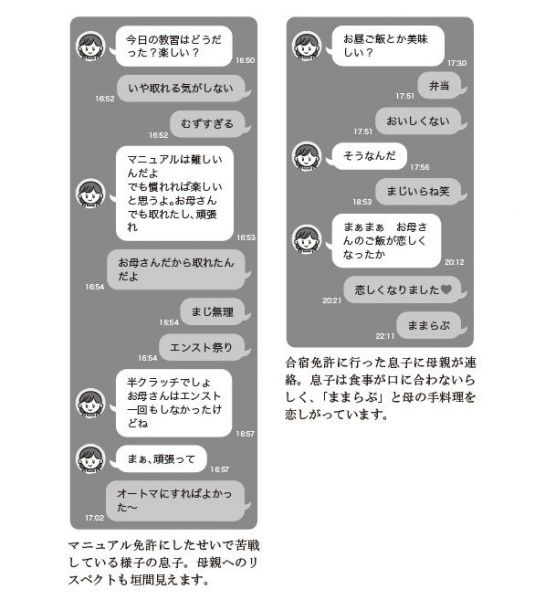――今回の若者調査では、幼い頃からの友達の存在感も増しているんですね。
一番仲の良い同性の友達について、出会ったのがいつかを尋ねると、「小学校」「小学校以前」が増えており、「高校時代より前」を合計すると9割にのぼりました。
つまり、「大学時代や社会人以降の友達」を一番親しいと答える人がきわめて少ないんです。
43歳の私からすると、価値観が同じような大学時代の友達が一番親しい感じがするので、衝撃的でした。
――家族や、小さな頃からつきあっている友達が重要視されている、ということですね。
学歴や職歴に左右されずに何でも話せる友達の存在が、すごく大事になっているんですね。
これはふたたび、家族みたいな血縁や「地縁」が再評価されている可能性があります。
仕事のように目的でつながっている関係性ではないので、退職しても関係性が切れることはありません。
――親とのつながりが深く、何でも相談する親の「メンターペアレンツ化」もそうですが、友達にも「否定しない関係性」というのを求めているのかなと思いました。
【インタビュー前編】「Z世代といえば…」それって思い込み?大きく変化したのは親子関係
https://withnews.jp/article/f0251104001qq000000000000000W02c10101qq000028357A
そうですね。「否定しない・されないこと」がとても大事で、親しい友達にはそういったつながりを求めています。
一方で、大学や会社のつながりなどは、「いつ切れるか分からないが、機能的にスキルアップする関係も大事」とビジネスライクにとらえている人もいます。