ARTICLE
本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業
(厚生労働省補助事業)として実施しています
(実施主体:朝日新聞社)

広告特集 企画・制作
朝日新聞社メディア事業本部
言語聴覚士は「話す、聞く、食べる」の専門家であり、失語症者の支援には欠かせない存在です。なかでも、脳梗塞(こうそく)をはじめとした脳の病気や頭部外傷による失語症が発症してすぐの、急性期と呼ばれる時期の支援は予後を大きく左右します。今回は愛媛県立中央病院で急性期の失語症者の支援を続けている三瀬和人さんに、お仕事や支援活動などを伺いました。
三瀬和人(みせ かずひと)さん
1984年、愛媛県生まれ。言語聴覚士。2011年から愛媛県立中央病院勤務。リハビリテーション部で失語症になってすぐの患者を支援する。2009年から愛媛県言語聴覚士会にも参加。現在、同会の副会長として、失語症者の支援や言語聴覚士の啓発活動に携わっている。
大学では法律を学んでいた三瀬さん。教養科目として履修した言語学の講義で、言語を獲得する過程と失う過程を知ったとき、失語症だった祖父との思い出が浮かんだそうです。
物心ついた頃から祖父は失語症で、コミュニケーションを取るのに困難が伴いました。「自分が食べたいアイスクリームの種類を、祖父はうまく伝えることができませんでした。その好みを知っていた私が、代わりに買いに行っていました」。言葉を交わすことはできないながらも、アイスクリームを介して通じるものはあったといいます。
当時は、言語聴覚士によるリハビリなどの支援もなく、失語症という言葉も一般的ではありませんでした。
言語聴覚士が国家資格となったのは1999年。そこから「話す、聞く、食べる」のに困難を抱える人々を支援する専門家として、たくさんの言語聴覚士が医療機関をはじめさまざまな支援の現場で働くようになりました。しかし三瀬さんの祖父は都市部から離れて暮らしており、定期的な通院も難しかったため、支援などを得られないまま亡くなってしまいました。
言語学の講義で祖父の失語症に合点がいった三瀬さんは、このとき初めて、言語を失うとはどういうことなのか、興味を持ったといいます。失語症に関わりたい、失語症者をサポートしたい、このとき抱いた思いが、言語聴覚士を志すきっかけとなりました。
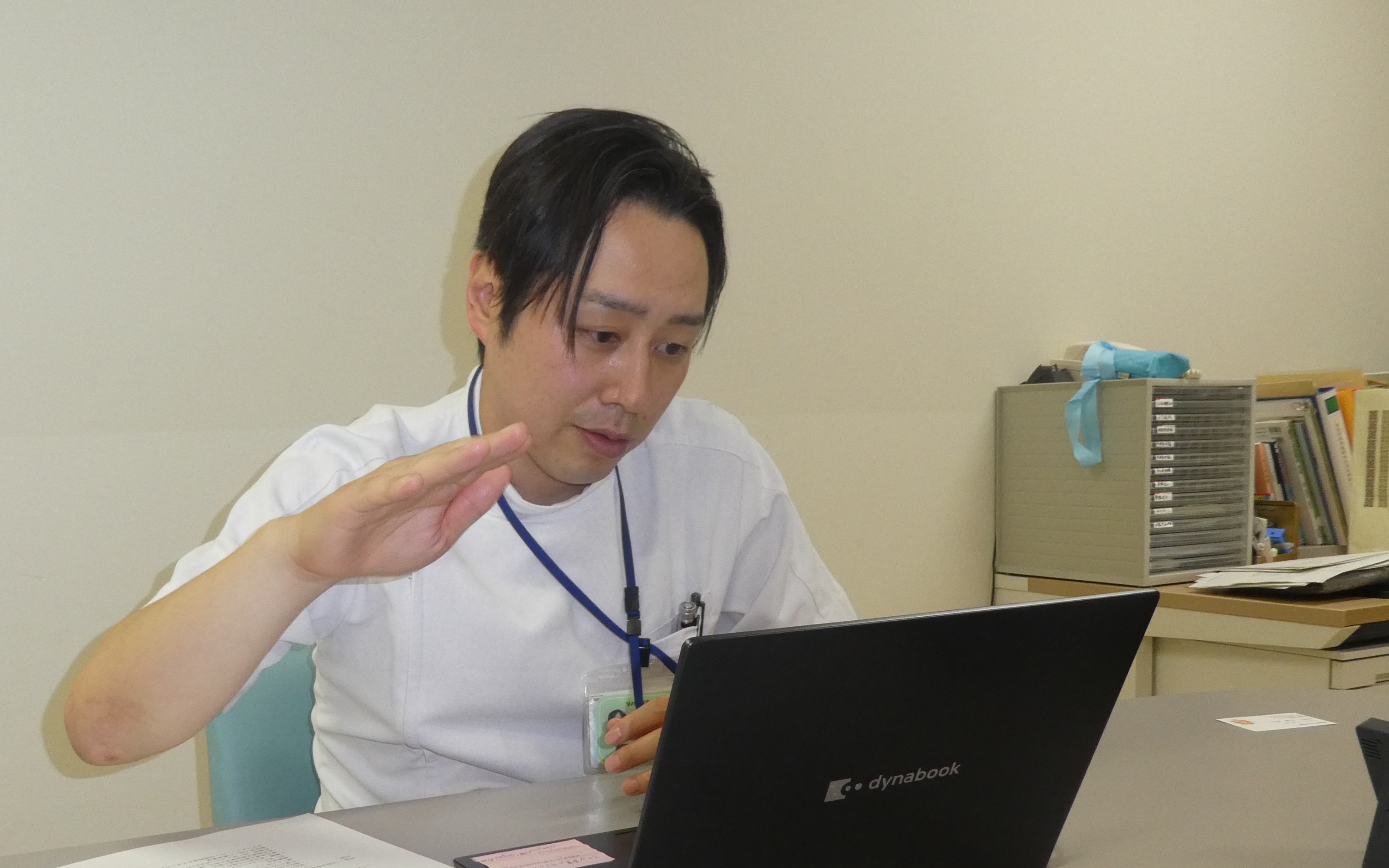
失語症者の支援は、失語症になってすぐの「急性期」、リハビリを集中的に行う「回復期」、自宅や入所施設での日常に戻っていく「生活期」に分けられます。三瀬さんが担当するのは「急性期」です。
定まった期間はありませんが、例えば脳梗塞などになってから症状が安定するまで、2~3週間というケースが多いようです。この時期は合併症のリスクや生命の危険もあり、本人も突然失語症になったことを受け止めきれないケースが多く、心身ともに不安定です。
「急性期」そのものはとても短いのですが、予後に大きく影響する大事な時期です。退院後も残された機能を使ってQOL(Quality of life=生活の質)を高める意欲を持てるよう、さまざまな工夫をしています。三瀬さんは、患者の「その後の人生すべてを考えて、対応しています」と話します。
「最初は表情が暗かったり、リハビリを拒否したりする方もいます。でもコミュニケーションを続けていくうちに表情が変わって、リハビリにも意欲を示してくれるようになると、やってきてよかったと嬉しくなります」
こうしてリハビリへの意欲を持ったうえで次の「回復期」に移ることで、よりよい予後を期待できるのです。

愛媛県内で活動する三瀬さんがいま直面している問題の一つは、言語聴覚士のなり手不足です。作業療法士や理学療法士と比べ知名度が低いのも、その理由の一つ。県内で2校あった養成校も1校となり、志願者は減少傾向です。都市部と地方間の偏在もあり、深刻な問題となっています。「失語症者支援に関わる言語聴覚士となると、さらにその数は小さくなってしまいます」
失語症者と言語聴覚士などの支援者で運営するコミュニケーションの場である「失語症友の会」が、事実上の活動停止に追い込まれた地域も少なくありません。また新型コロナウイルスの感染拡大は、言語聴覚士同士の対面での勉強会や交流の機会も大きく減少しました。
現状を打開しようと、三瀬さんは愛媛県言語聴覚士会の一員として、小中学生への啓発活動やCM動画の制作などに取り組んでいます。職業体験のイベントに出て、介護食を食べてもらったり、脳の機能を説明したりして、「話す」・「聞く」・「食べる」を支える言語聴覚士の仕事を知ってもらいます。イベントでは、脳トレのような検査に興味を持った子どもやその保護者らが多く集まるそうです。
オンラインセミナーの普及で、言語聴覚士同士が対面する機会も減ってしまったそうですが、いま、対面での勉強会を少しずつ再開しているといいます。同じ地域で働く仲間と交流し学び合う機会から得られるものは大きく、それにより地域での連携もしやすくなるそうです。

言語聴覚士の業務内容は多岐にわたります。三瀬さんも病院では、失語症ではない方のリハビリを多く担当しており、失語症者一人ひとりに長く関わっていくことが難しい状況もあります。その中で三瀬さんは、「生活期」の失語症者を息長く支援する重要性を指摘します。
「生活期」、つまり施設や自宅で日常を送っている失語症者は、出かけたり人と会ったりする頻度が少なくなりがちで、回復のための刺激を得にくい状況に陥るそうです。家族が遠方に住んでいて会いに行くのが難しい、車社会で一人では出かけられない、身体にまひが残って出かけにくい、など事情はそれぞれです。
ある失語症者は、三瀬さんのサポートで博物館を訪れた際、「外出は1年ぶりだ」と伝えてくれたそうです。それくらい出歩かなくなっている。三瀬さんはこの外出機会の減少を危惧しています。
「長期にわたって回復していく失語症者にとって、外出で得られる刺激はとても貴重です。人と会い、コミュニケーションを交わして、社会と関わる。失語症者がこうした日常生活を送るためには、言語聴覚士や意思疎通を支援する人たちのサポートが欠かせません」
高齢化や子どもの言語発達への関心の高まりもあって、コミュニケーション支援のニーズは増えているといいます。言語聴覚士や意思疎通支援に興味を持つ人に向けて三瀬さんは呼びかけます。「この仕事は言葉の響きからコミュニケーションが得意でないとできないと思われがちですが、そんなことはありません。先人たちが作ってきた失語症者支援の輪を保ちにくくなっている地域が増えています。ぜひ私たちの仲間になって、支援の輪を一緒につないでいってほしいです」
本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業
(厚生労働省補助事業)として実施しています
(実施主体:朝日新聞社)